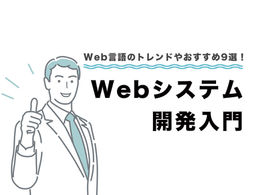【完全解説】BubbleでSaaS開発は可能?費用・期間・事例・リスクまで徹底検証
- シースリーレーヴ編集者

- 2025年9月5日
- 読了時間: 21分
更新日:2025年9月6日
SaaSを立ち上げたい――でも、フルスクラッチでの開発は「数千万円・半年以上」が当たり前。
そんな大きな負担を前に、もっと早く・低コストでリリースできる方法を探している方は多いのではないでしょうか。
そこで近年注目されているのが、ノーコードツール 「Bubble」 を使ったSaaS開発です。
プログラミング不要で本格的なサービスを構築できることから、スタートアップや新規事業の現場で導入が加速しています。
しかし、実際に検討を始めると次のような疑問や不安が出てきます。
「Bubbleで本当にSaaSは作れるの?」
「費用や期間はどのくらいかかる?」
「ユーザーが増えても対応できるのか?」
「外注するなら、どんな開発会社を選ぶべき?」
これらの不安を解消しなければ、安心してプロジェクトを前に進めることはできません。
本記事では、BubbleによるSaaS開発について メリット・デメリット・開発手順・費用感・成功事例・リスクと対策 までを徹底解説します。 読み終えたときには、あなたの状況にあわせて 「BubbleでSaaSを開発すべきか、どう進めるべきか」 が明確になるはずです。
BubbleでSaaSを“短期×適正コスト”で。まずは要件をお聞かせください。
目次案
SaaSに必要な機能一覧
Bubbleで実現できる範囲と制約
メリット
デメリット
競合記事との差別化
企画・要件定義 → プロトタイプ → MVP開発 → 本番リリース
Multi-tenant構成 vs Sub App構成
App Connectorを使った外部サービス連携の実際
規模別:開発期間と費用の目安
小規模SaaS
中規模SaaS
大規模SaaS
工数の内訳
海外事例(Flexiple, TicketRev, Plato など)
国内事例
リモートHQ
SANU 2nd Home
ブラリノ
弊社事例
課金モデル
ユーザー拡大に伴うシステムの伸ばし方
外部連携・プラグイン活用の戦略
想定以上のユーザー増加によるパフォーマンス低下
セキュリティ/認証設計の甘さ
運用・保守体制の不足
対策
発注先を選ぶ基準:実績・SaaS開発経験・セキュリティ対応力
「単なるプロトタイプ開発会社」との違いに注意
契約前に確認すべきこと
1. BubbleでSaaS開発は可能?結論から解説

結論から言えば、Bubbleを使ってSaaS開発は十分に可能です。
実際に国内外では、Bubbleを活用して短期間で立ち上げたSaaSが資金調達に成功したり、数万人規模のユーザーを抱えるサービスへと成長した事例も出てきています。
ではなぜBubbleでSaaSが作れるのか。
その理由を理解するために、まずは一般的なSaaSに必要な機能と、Bubbleでどこまで実現できるのかを整理してみましょう。
SaaSに必要とされる代表的な機能
SaaS(Software as a Service)としてサービスを展開する場合、以下のような機能が欠かせません。
会員管理機能:ユーザー登録・ログイン、プロフィール編集、パスワードリセットなど
決済機能:クレジットカード決済、サブスク課金、請求書発行など
権限管理機能:管理者/一般ユーザー/企業アカウントなど、利用者ごとのアクセス制御
データベース機能:ユーザーごとのデータ保存、検索、レポート表示
API連携:外部サービス(決済、メール送信、分析ツール、AIサービスなど)との連携
UI/UX設計:レスポンシブ対応、直感的な操作ができる画面デザイン
運用・セキュリティ:データのバックアップ、SSL通信、ログ監視など
これらはSaaSを「使えるサービス」として継続的に運営していく上で必須の要素です。
Bubbleで実現できる範囲
Bubbleはノーコードながら、上記の機能をほぼすべてカバーする仕組みを備えています。
会員管理 → ユーザーデータベースとワークフロー機能により、サインアップ・ログインを簡単に構築可能。
決済 → StripeやPayPalといった外部サービスとのAPI連携、プラグインを利用してサブスク課金にも対応。
権限管理 → ロール設定や条件分岐を組み合わせ、管理者・利用者などのアクセス制御を実装可能。
データベース → アプリ内に柔軟なデータベースを持ち、検索や条件抽出もノーコードで設定可能。
API連携 → App Connector機能で外部サービスとシームレスに連携。決済・CRM・分析ツールなどと組み合わせられる。
UI/UX → ドラッグ&ドロップでデザインを作成、レスポンシブ対応も可能。
Bubbleの制約と注意点
一方で、Bubbleには以下のような制約や注意点もあります。
高トラフィック時の負荷:数十万ユーザー規模の同時アクセスでは、速度や安定性に課題が出ることもあります。
複雑なバックエンド処理:大量データの高速処理やAIモデルの学習など、Bubble単体では対応しにくい場合がある。
プラットフォーム依存:Bubble上で構築したアプリは、Bubbleのサービス基盤に依存するため、自由度はスクラッチ開発より低い。
ただし、これらは「解決不能な壁」ではなく、API連携や外部サービスとのハイブリッド構成によって克服可能なケースも多くあります。
この章のまとめ
SaaSに必要な機能(会員管理・決済・権限管理・API連携など)は、Bubbleでほぼ実装可能。
ノーコードでもUI/UX設計や外部サービスとの連携が柔軟に行える。
一方で、大量データ処理や高トラフィック対応には制約があり、外部サービスやAPI連携で補完する必要がある。
初期段階でMVPを素早く立ち上げるには特に有効な選択肢。
要件が固まっていなくても大丈夫です。ヒアリングを元に最短ルートをご提案します。
2. BubbleでSaaS開発を行うメリット・デメリット

SaaS開発を検討する際に最も気になるのは、「Bubbleを使うことでどんな利点があるのか、逆にどんなリスクがあるのか」という点です。ここでは、実際のプロジェクト経験や事例から見えてきた メリットとデメリット を整理します。
BubbleでSaaS開発を行うメリット
短期開発が可能
ドラッグ&ドロップでUIを構築でき、コードを書かずに機能を実装できるため、従来の1/3の期間でリリース可能。
MVP(最小実用製品)を数ヶ月で市場投入し、ユーザーの反応を早期に得られる。
低コストでの開発
スクラッチ開発と比べて初期投資を大幅に抑えられる。
スタートアップや新規事業で「まずは試す」段階に最適。
スピード検証に強い
開発途中でも画面を即時に動かして確認できるため、仕様変更や改善を柔軟に反映できる。
ユーザーからのフィードバックを短期間で実装可能。
UI/UX改善の容易さ
デザインの修正や画面追加が簡単。
デザイナーや非エンジニアがプロダクト改善に関わりやすく、チーム全体でUI/UXを磨きやすい。
BubbleでSaaS開発を行うデメリット
スケーラビリティの制約
同時アクセス数が数万規模に増えると、レスポンス速度や安定性に課題が出ることがある。
API連携や外部サーバーとの組み合わせで補強する必要がある。
高トラフィック時のパフォーマンス低下
データベースクエリが複雑化すると処理速度が落ちるケースがある。
最初からパフォーマンス設計を意識しておかないと、リリース後に「遅い」と感じられるリスク。
セキュリティの懸念
標準機能でSSLやユーザー認証は備わっているが、脆弱性診断や細かな権限管理は外部対応が必要な場合もある。
特にBtoB SaaSや金融系サービスでは、Bubble単体では要件を満たせず追加開発が必須となるケースも。
実際に発生しやすい「失敗例」
ユーザー急増による速度低下
→ 初期に想定していたより利用者が急増し、画面表示が遅くなった。後から外部DB接続やサーバー強化を検討することに。
機能を盛り込みすぎて開発停滞
→ ノーコードで自由に作れる分、機能追加を繰り返してしまい、結果的に開発期間が長期化。
→ SaaSは「まずリリースして検証」が鉄則。優先順位付けが重要。
外注先の知識不足によるトラブル
→ Bubble経験の浅い制作会社に依頼した結果、設計が甘く、ユーザー増加時に不具合が多発。
→ 発注時には、SaaS実績やスケール経験を持つ会社かを確認することが不可欠。
この章のまとめ
Bubbleは 短期開発・低コスト・柔軟な改善 に強く、SaaSの初期立ち上げに非常に向いている。
ただし、スケーラビリティやパフォーマンス、セキュリティには制約があり、外部連携や設計の工夫が欠かせない。
実際に失敗しやすいのは「想定以上のユーザー増」「機能追加のしすぎ」「知識不足の外注」など。 → メリットとデメリットを理解した上で、適切なパートナーや開発計画を選ぶことが成功の鍵となる。
3. BubbleでのSaaS開発プロセス

BubbleでSaaSを開発する場合、従来のシステム開発と同様に段階を踏んで進めていきます。ノーコードだからといって場当たり的に作り始めると失敗するリスクが高いため、「企画 → プロトタイプ → MVP → 本番リリース」という流れを押さえることが重要です。
1. 企画・要件定義
まずは「どんな課題を解決するSaaSなのか」「誰に使ってもらうのか」を明確にします。
必要な機能を洗い出し、必須機能(ログイン、課金など)と後回しでよい機能(通知、拡張レポートなど)を切り分けることが重要。
この段階で優先順位を誤ると、リリースが遅れたり、コストが膨らむ原因になります。
2. プロトタイプ作成
BubbleはUI設計が得意なため、早い段階で画面モックアップを作成できます。
プロトタイプは「動くデザイン見本」として、ユーザーインタビューや社内共有に役立つ。
この段階で「使いにくい」「想定と違う」という意見を集めることで、開発後の手戻りを減らせます。
3. MVP開発(最小限の機能で市場投入)
SaaSの根幹となる機能(会員登録、ログイン、課金、メイン機能)だけを実装。
目的は「早くリリースしてユーザーに触ってもらい、検証すること」。
Bubbleなら数ヶ月でMVPを完成させることが可能です。
4. 本番リリースと運用
ユーザーからのフィードバックをもとに改善を繰り返します。
初期のリリースは完全版を目指す必要はなく、**「市場で実際に使えるレベル」**を意識するのが成功のコツです。
運用段階では、Bubbleのログや外部分析ツールを組み合わせてモニタリングすることが推奨されます。
◆Multi-tenant構成 vs Sub App構成
SaaS開発では「1つのアプリで複数ユーザー(企業)を管理する」か「クライアントごとに別アプリを用意する」かを選択する必要があります。
Multi-tenant構成
単一アプリで複数テナントを管理。
コストが低く、管理もシンプル。
ただし、セキュリティ設計や権限管理を誤ると「他社のデータが見えてしまう」リスクがある。
Sub App構成
Bubbleの「Sub App機能」を利用し、親アプリを基盤にクライアントごとに独立したサブアプリを展開。
データが完全に分離されるため、セキュリティ面で安心。
一方で、BubbleのProductionプラン(月額$529〜)が必須で、コストは高くなる。
規模や利用ユーザー数、セキュリティ要件に応じて、どちらを選ぶかを決める必要があります。
◆App Connectorを使った外部サービス連携
SaaSでは、外部サービスとの連携が必須になるケースが多くあります。
例えば
決済連携:StripeやPayPalを使ったサブスク課金
メール配信:SendGridやGmail APIによる通知・リマインダー
分析ツール:Google AnalyticsやAmplitudeとのデータ連携
Bubbleの「App Connector」を使えば、これらの外部APIを簡単に統合できます。 特にSaaSでは、「自前ですべて作るより外部サービスとつなぐ方が圧倒的に効率的」なケースが多いため、API活用は必須の戦略といえます。
この章のまとめ
BubbleでのSaaS開発は「企画 → プロトタイプ → MVP → 本番リリース」という流れで進めるのが基本。
構成は Multi-tenant(低コスト・柔軟)か Sub App(セキュリティ重視・高コスト) のいずれかを選択。
外部サービスとのAPI連携は、SaaSに必須。App Connectorを活用することで効率的に拡張できる。
4. 開発期間と費用の目安

SaaS開発を検討している方が必ず気になるのが、「どのくらいの期間と費用でリリースできるのか」という点です。Bubbleを活用することで、フルスクラッチに比べて開発コストを抑えつつ、短期間でのリリースが可能です。
以下に、規模別の目安を整理しました。
◆規模別:開発期間と費用の目安
小規模SaaS(例:マッチングサービス、予約管理アプリ)
開発期間:約3ヶ月
費用目安:300〜500万円
特徴:基本的なユーザー登録、検索、予約機能、決済などを搭載。スタートアップやスモールビジネスのMVPに最適。
中規模SaaS(例:サブスク管理システム、BtoB業務ツール)
開発期間:約4〜6ヶ月
費用目安:500〜800万円
特徴:複数のユーザー権限、レポート機能、外部サービスとのAPI連携などを組み込み、業務利用に耐えるレベル。
大規模SaaS(例:複数ユーザー企業向けサービス、カスタマイズ性の高いBtoB SaaS)
開発期間:6ヶ月〜
費用目安:800万円以上
特徴:Sub App構成や外部DBとの連携を前提に、セキュリティやパフォーマンスを強化。大企業や高負荷を想定したシステム。
工数の内訳
Bubbleでの開発でも、システム開発の流れは基本的に同じです。費用の目安は以下の工数に分解できます。
要件定義(全体の15〜20%)
サービスの目的や機能要件を整理
必須機能と将来的に追加する機能を切り分け
SaaS特有の課金モデルや権限管理を設計
デザイン(全体の15〜20%)
ワイヤーフレームやUI設計
ユーザーが直感的に操作できる画面設計
モバイル・タブレット対応のレスポンシブ調整
開発(全体の40〜50%)
データベース設計、ワークフロー実装
決済・API連携・権限管理などの機能開発
外部サービスとの接続やプラグイン導入
テスト(全体の10〜15%)
単体テスト・結合テスト・ユーザーテスト
セキュリティや権限周りの確認
高負荷テストは必要に応じて実施
運用・保守(全体の10〜15%)
初期リリース後の改善サイクル
ユーザーフィードバック対応
サーバーやパフォーマンスの監視
この章のまとめ
小規模SaaSは3ヶ月/300〜500万円、中規模は4〜6ヶ月/500〜800万円、大規模は6ヶ月以上/800万円以上が目安。
Bubbleを使うことで、スクラッチ開発に比べて大幅に短縮可能。
費用は「要件定義・デザイン・開発・テスト・運用」に分かれ、規模や機能数によって変動する。 → 早期にリリースし、市場で検証したいならBubbleは特に有効な選択肢。
あなたのケースはどの規模・どの期間に当てはまる?
5. 国内外の成功事例

Bubbleは、世界中で数多くのSaaS開発に活用され、実際に大きな成果を上げてきました。
この章では、海外・国内での代表的な成功事例、そして弊社が手がけたBubble開発の実績をご紹介します。
すべてBubbleで構築されたサービスだからこそ、皆さまも具体的にイメージしやすいと思います。
海外の成功事例
TicketRev(チケットレビュ)
特徴:「購入者が価格を提示する逆オークション型」のチケットマーケットプレイス。
開発時間:わずか2ヶ月でBubble上にMVPを開発し、コスト・品質・スピードを重視した構築を実現。
成果:ローンチ後、2020年に1.1百万ドル(約1.1億円)のプレシード資金を調達し、ファンとの距離を縮める革新的サービスとして成長。
Flexiple
特徴:企業と優秀なフリーランスをつなぐマッチングプラットフォーム。最初は手動から始まり、最終的にBubbleへ統合。
成果:年商300万ドル(3億円規模)を達成し、支払い額も600万ドル以上に。ユーザーの時間を40,000時間以上節約した事実が、Bubbleを本格運用に耐えるプラットフォームと証明。
国内の成功事例
国内でもBubble活用による本格的な成功事例が増えています。それぞれ資金調達や事業売却に直結したプロジェクトです。
リモートHQ:Bubbleで開発し、約2億円の資金調達を実現。
SANU 2nd Home:Bubbleを活用した構築により、50億円という大規模資金調達に成功。
ブラリノ:結婚準備向けアプリとしてBubbleで開発され、リリース後にバイアウト(事業売却)を果たした画期的事例。
シースリーレーヴ(弊社)のBubble開発実績
サービス名 | 内容 | 開発期間 | 費用目安 |
Twinq | SNS連動の画像二択投票+属性分析 | 約1ヶ月 | 100〜200万 |
ブラリノ | Web招待状や写真共有などを含む結婚準備アプリ | 約2ヶ月 | 200〜300万 |
TRIP BOOK | 旅行スケジュール共有+目的地情報アプリ | 約2ヶ月 | 300〜400万 |
ReMoCe | MC依頼・決済・打ち合わせまで完結できるサービス | 約1ヶ月 | 200〜300万 |
Kitene | Twitter連携型の人材マッチング | 約1ヶ月 | 100〜200万 |
AI営業ロープレラボ | AIを用いた営業トレーニングプラットフォーム | 約3ヶ月 | 200〜400万 |
AI占いサービス | 占星術プランを提供する占いアプリ | 約2ヶ月 | 100〜200万 |
bond | BtoBビジネスマッチングSaaS | 約4ヶ月 | 500〜700万 |
アート特化型SNS | 投稿・交流機能を備えたアートSNS | 約4ヶ月 | 400〜600万 |
Kifto | NFT寄付プラットフォーム(OpenSea/API連携含む) | 約3ヶ月 | 200〜400万 |
目的に近い事例を基に、最短スコープとスケジュールをご提案します。
6. 収益化とスケールのポイント

SaaSを立ち上げた後に重要になるのは、安定した収益を生み出しながら、ユーザー数の増加に耐えられる仕組みを整えることです。ここでは、代表的な課金モデルから、スケールの考え方、そしてBubbleを使った拡張の工夫を解説します。
課金モデルの選択肢
SaaSの収益化では、以下のような課金モデルが一般的です。
サブスク課金 月額・年額で利用料金を定額に設定するモデル。最も多く採用されており、安定収益を確保しやすい。
例:月額1,000円で継続利用できるタスク管理ツール
従量課金 利用した分だけ料金が発生するモデル。利用頻度やデータ量に応じて課金できるため、BtoB SaaSに向いている。
例:送信メール数やAPIリクエスト数に応じて課金
フリーミアム 基本機能は無料で提供し、追加機能や上位プランで課金するモデル。新規ユーザーを獲得しやすく、成長フェーズで効果的。
例:無料プランで利用開始 → 高度なレポート機能は有料
BubbleではStripeやPayPalなどの決済サービスと簡単に連携できるため、これらの課金モデルをスムーズに導入できます。
ユーザー拡大に伴うシステムの伸ばし方
サービスが成長すると、ユーザー数やアクセス数の増加に応じてパフォーマンス課題が発生します。Bubbleでスケールさせるためには、以下の工夫がポイントです。
データベース設計を最適化する 不要なデータの読み込みを避け、条件検索やフィルタリングを効率化。
Multi-tenant構成とSub App構成を使い分ける 少人数向けサービスはMulti-tenantで効率化、大規模BtoB SaaSはSub Appでクライアントごとに分離し、セキュリティと安定性を確保。
必要に応じて外部サービスを併用 大規模データ処理や画像変換などは、外部のサーバーやクラウドサービスにオフロードすることで、Bubbleの負荷を軽減できる。
外部連携・プラグイン活用の戦略
Bubbleの強みの一つは、API連携やプラグイン活用によって容易に機能を拡張できる点です。
決済連携:StripeやPayPalでのサブスク課金や従量課金を導入。
メール通知:SendGridなどの外部サービスで大量配信を効率化。
分析・計測:Google AnalyticsやAmplitudeとの連携で利用状況を可視化。
その他プラグイン:チャット機能、スプレッドシート連携、AI API活用などを追加し、ユーザー体験を強化。
これらを柔軟に組み合わせることで、初期は小規模にスタートし、ユーザー拡大に合わせて機能を増やしていく「スモールスタートからのスケールアップ」が可能になります。
この章のまとめ
SaaSの収益化は「サブスク」「従量課金」「フリーミアム」などが代表的で、BubbleはStripe連携により導入が容易。
スケールの鍵は、データベース最適化・構成選択・外部サービスの活用にある。
プラグインやAPIを使えば、サービスを成長に合わせて柔軟に拡張できる。
7. よくある失敗とリスク・その対策
BubbleでSaaSを開発する際、多くの企業が共通して直面する落とし穴があります。ここでは、特に発生しやすい失敗とリスクを取り上げ、その回避策を解説します。
想定以上のユーザー増加によるパフォーマンス低下
リリース直後は問題なく動いていたのに、ユーザー数が急増すると「画面が重い」「読み込みが遅い」といった声が増えることがあります。これは、Bubbleのデータベース設計やワークフロー処理が大量アクセスに最適化されていない場合によく起こります。
対策
データベースの最適化:検索条件の工夫や不要データの分離で処理を軽くする。
バックエンド処理の分散:大量データの計算や処理は、外部サーバーやAWSなどにオフロード。
ユーザー急増を想定した負荷テストを事前に行う。
セキュリティ/認証設計の甘さ
標準でユーザー管理機能を持つBubbleですが、設定を誤ると「ユーザー権限が甘く、他社データが閲覧できてしまう」といったリスクが発生します。特にBtoB SaaSや金融系サービスでは致命的な問題になりかねません。
対策
権限設計の徹底:ユーザーロールごとのアクセス権限を正しく定義。
外部認証サービスとの併用:Auth0などを組み合わせてセキュリティを強化。
定期的なセキュリティ診断を行い、脆弱性を早期に発見する。
運用・保守体制の不足
SaaSはリリースして終わりではなく、ユーザーからのフィードバックを反映し、改善を続けることが欠かせません。ところが、運用・保守を十分に想定していないと「リリース後に不具合対応で手が回らない」という状況に陥ります。
対策
改善サイクルの計画:リリース後も定期的に機能改善・不具合修正を行う体制を構築。
モニタリングの強化:アクセスログやエラーログを常時監視し、問題を早期に検知。
外注パートナーとの長期的な契約により、運用フェーズも見据えた支援を受ける。
この章のまとめ
ユーザー増加での速度低下は、データベース最適化や外部サーバー活用で防ぐ。
セキュリティの甘さは、権限設計と外部認証サービスの導入でカバーできる。
運用・保守不足は、改善サイクルとモニタリング体制を整えることで解決可能。 → Bubbleの弱点を理解し、適切な補強策を組み合わせることで、安心してSaaSを成長させることができます。
スケールやセキュリティを見据えた“失敗しない設計”を無料でご提案します。
8. Bubble開発を外注する際のチェックポイント
BubbleでSaaSを開発したいと考えても、「社内にノーコードの専門人材がいない」「スピード重視で外部に依頼したい」というケースは多くあります。その際に重要になるのが、外注先の選び方です。ここを誤ると、せっかくのプロジェクトが停滞したり、リリース後に不具合対応に追われることになりかねません。
発注先を選ぶ基準
実績
これまでにどんなアプリを開発してきたか、特に SaaS領域の実績 があるかを確認しましょう。
「社内ツール」や「簡単なLP」程度しか経験がない場合、本格的なSaaSを構築するにはノウハウ不足の可能性があります。
SaaS開発経験
サブスク課金、ユーザー管理、API連携といったSaaS特有の要件を理解しているかは大切なポイントです。
事例として 課金システムや権限管理を含むアプリを手掛けているかを確認すると安心です。
セキュリティ対応力
権限設定、データ分離、脆弱性診断などを考慮して開発できるかどうか。
BtoB SaaSでは特に、セキュリティ要件を満たせないとビジネスに直結するリスクとなります。
「単なるプロトタイプ開発会社」との違いに注意
最近は「数日でアプリを作ります」とうたう開発会社も増えていますが、多くはMVPレベルの簡易アプリを短期間で作ることに特化しています。 そのような会社に本格的なSaaS開発を依頼すると、次のような問題が起こりがちです。
ユーザーが増えた途端に動作が不安定になる
セキュリティ要件を満たせず、商用利用に耐えられない
運用・改修に対応できない
本格的なサービスを作りたいなら「プロトタイプ専門」ではなく「SaaS開発を伴走できるパートナー」を選ぶことが重要です。
契約前に確認すべきこと
見積もり範囲
デザイン、開発、テスト、運用まで含まれているか。
「初期開発のみ」で終わらないように注意。
運用体制
リリース後も改善やバグ修正に対応してくれるか。
定期的なレビューやアップデートが可能か。
改修対応可否
仕様変更や機能追加に柔軟に対応できるか。
長期的な関係を前提にしたサポート体制があるか。
この章のまとめ
外注先は 実績・SaaS開発経験・セキュリティ対応力 を基準に選ぶこと。
「プロトタイプ専門会社」に依頼すると、商用SaaSでは不具合が起こりやすい。
契約前には 見積もり範囲・運用体制・改修対応 を必ず確認しておく。
→ 適切なパートナーを選ぶことで、Bubbleを使ったSaaS開発はスピードも安心感も大きく向上します。
9. まとめ|BubbleでSaaS開発を成功させるには?
ここまで、Bubbleを活用したSaaS開発について、基本的な仕組みからメリット・デメリット、費用感や成功事例、外注のポイントまでを解説してきました。最後に、本記事の要点を振り返りましょう。
◆本記事での要点まとめ
・BubbleでSaaS開発は可能
会員管理・決済・API連携など必須機能をノーコードで実装できる。
・メリット
短期間で開発でき、コストを抑えながら市場検証が可能。
・デメリットとリスク
スケーラビリティやセキュリティ面に制約があり、外部サービスや設計の工夫が必要。
・開発プロセス
「企画 → プロトタイプ → MVP → 本番リリース」の流れが基本。
・費用・期間の目安
小規模は3ヶ月/300〜500万円、中規模は4〜6ヶ月/500〜800万円、大規模は6ヶ月〜/800万円以上。
・成功事例
国内外で資金調達や事業売却につながった実例が多く存在。
・収益化・スケール
課金モデルの工夫とAPI・プラグイン活用で成長に合わせて拡張可能。
・失敗回避
ユーザー増加時のパフォーマンス低下やセキュリティ不備を事前に対策することが重要。
・外注のチェックポイント
実績・SaaS経験・セキュリティ対応力を基準に、長期的に伴走できるパートナーを選ぶ。
Bubbleを活用することで、「スピード × コスト最適化 × 実現性」 を同時に叶えられます。
従来なら半年〜1年かかる開発を数ヶ月で実現し、数千万円規模の費用を抑えられるのは、スタートアップや新規事業にとって大きな魅力です。
SaaS立ち上げを検討している方は、まず 要件整理から始めること をおすすめします。
「どんな課題を解決したいのか」「必須機能と追加機能をどう切り分けるか」を明確にすれば、Bubbleでの開発は格段に進めやすくなります。
「アイデアを素早く形にし、事業として成長させる」
――その実現手段として、BubbleはこれからのSaaS開発において強力な選択肢となるでしょう。
Bubble開発ならシースリーレーヴ株式会社へ

弊社は Bubble/FlutterFlowを活用した開発に強みを持ち、国内外で多数の実績があります。
無料で見積もり相談も可能ですので、まずはお気軽にご要件をお聞かせください。
内容をもとに、最適な開発プランをご提案いたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました!